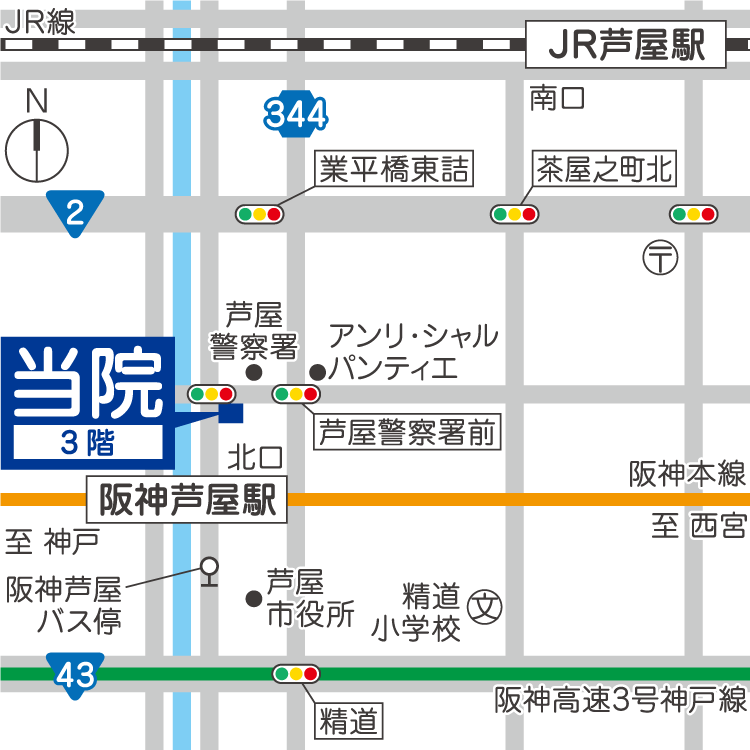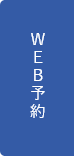胸やけと逆流性食道炎 胃食道逆流症(GERD)とは

「胸やけがする・・」や「酸が上がってくる・・」症状は、胃の内容物、特に胃酸が食道に逆流することが原因の一つです。
これらの症状を酸逆流症状といいます。酸逆流症状には、「すっぱいものがこみ上げる」「胸の痛み」「つかえる感じ」「せき」「声がかすれる」「耳のあたりの痛み」などがあります。
そして、胃の内容物が食道に逆流して起こる病気の総称を
「胃食道逆流症(gastro-esophageal reflux disease)」
といいます。医師の間では、英語の頭文字を略語でGERD(ガード)というよび方をしています。
胃食道逆流症(GERD)
胸やけの症状のほか、食道を内視鏡で見たとき、胃酸のために食道粘膜がただれ、炎症がある場合は「逆流性食道炎」と診断されます。
胸やけなどの不快な症状があり、食道粘膜に炎症がない場合は「非びらん性胃食道逆流症」と診断されます。
胃食道逆流症を繰り返していると・・・
炎症がおこって回復する過程で、食道に胃粘膜と同じような上皮が現れてくる場合があります。これを「バレット食道」と呼びます。
これ自体は悪性ではありませんが、そこに「食道がん」ができる可能性が高くなります。欧米では食道がんの原因の半数以上がこのバレット食道だとされています。
バレット食道は治療によって改善することは少なく、バレット食道にならないために胃食道逆流症を放置しないことです。
逆流性食道炎、胃食道逆流症(GERD)の診断
逆流性食道炎、胃食道逆流症(GERD)は、「胸やけ」や「呑酸(どんさん)」といった症状と「内視鏡検査」で診断します。
胸の痛みや食物がつかえるなどの症状は、逆流性食道炎以外の食道疾患や耳鼻咽喉科疾患、心臓疾患などにもみられることがあります。
“単なる胸やけ”と片づけず、気になる症状がある場合は医師の診察を受けることが大切です。
逆流性食道炎、胃食道逆流症(GERD)の治療
逆流性食道炎の治療は、大きく分けておくすりによる治療と、手術による治療がありますが、多くの場合、おくすりによる治療で症状が改善します。
逆流性食道炎を放置することは、「胸やけ」や「呑酸(どんさん)」が持続することであり、生活の質が低下します。自然に軽快するものもありますが、重症化する場合もありますので、早めの治療が有効です。
症状がなくなったからといって、自分の判断で勝手に服用をやめてしまうと、ほとんどの人はすぐに再発してしまいます。逆流性食道炎の治療では、医師の指示にしたがってきちんと薬を飲み続け、炎症を完全に治し、維持することが大切です。
手術を行う場合
- 薬物治療が効かない
- 大きな食道裂孔(れっこう)ヘルニアにより、前かがみや横になった際に、胃の内容物が戻ってしまう
- 薬が有効でも長期間の使用を避けたい患者さん
胸やけ、胃酸の逆流を防ぐには
胸やけを起こさないためには、毎日の生活にも注意をしましょう。
ポイントは、① 食事、②
姿勢、③ おなかを圧迫しない、ことです。
毎日の生活を改善するだけでよくなることがあります。
① 食事と嗜好品の注意 - 大食を避け、嗜好品は控えめに -
食事は一度にたくさん食べずに、ゆっくりと。
また、食べすぎも避けましょう。タバコ、アルコール飲料、コーヒー、チョコレート、香辛料の多い食べ物や脂肪の多い食べ物、柑橘類なども控えるとよいでしょう。
② 姿勢の注意 - 昼間の姿勢・就寝時の姿勢 -
前かがみの姿勢を避けましょう。
食事の後、すぐに横にならないようにしましょう。
就寝時にベッドの上半身(頭側)を挙げましょう。就寝時は左側を下にしましょう。
③ おなかの圧迫への注意 - 締め付けない -
ベルトや帯、コルセットはゆるめにしましょう。
太り気昧の方は、体重を減らしましょう。